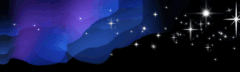
インドベンガル地方にトラの生息域がある。
ベンガル地方はのべ○平方キロにもおよぶ広大な地域であり、数多くの動物たちが生息している。
これはそこに住む俗称ベンガル虎と、彼ら同族たちの人間に対する逆襲の物語である。
虎は今日も獲物を探していた。いつもの日課である。
それが彼らの仕事であり、その日一日、いかに獲物を捕らえ、喰らい、自らのテリトリーを守り、おのれのライバルを倒すかが天命ともいうべきライフワークなのだ。
鹿の臭いを嗅ぎつけた。虎は臭いを嗅ぎわけ、それをたどって、密林を柔軟な身体で蛇身のごとくすり抜けつつ、何キロも彷徨い(さまよい)歩いた。
その虎は鹿を確認し、猫這い姿勢で一点に集中し、じょじょに彼我の距離をつめていった。
オスの虎の臭いがする。にわかに虎のアドレナリンが体中を駆け巡り、思わず虎は生唾を飲み込んだ。
虎はどうどうと敵の前に姿を現し、一声咆哮(ほうこう)した。
敵は一瞬、反射的に身をひくめ、目を見開いてライバルのほうを凝視した。虎はやにわに敵に襲いかかった。前足で相手を押さえつけ、喉元に食らいつくのが常道だが、あごの力が強い彼らは、ところかまわず食らいつく。 窒息するか、出血多量で死ぬのを待つか、逃げられても何度も攻撃し、動けなくなってから、生きていようが死んでいようが、かまわずむさぼり食う。 食べている最中で、ライバルが現れ獲物を横取りされることもある。またその逆も。そんなことを日夜繰り返しており、それが彼らの人生である。 その夜、ベンガルタイガーの密林は、虫の声、鳥のさえずり一つ聴こえず、不気味なほどの静寂に包まれていた。水牛の大きさに迫るほどの体躯(たいく)を誇る彼が、何者かに脅えていた。 。やがて重圧感が辺りを支配し、虎を包み込んだ。ベンガルタイガーは見えないがたしかにいるその存在に対し、ついにこらえきれず、攻撃を開始した。四囲に向かって唸りを発していると、どこからともなく、死臭が漂い始めた。虎はこれは人間の腐った臭いだと確信した。前に人間たちの戦った跡に行ったことがあるのだ。寝そべったまま、しきりにあたりを威嚇した。今度は火薬の臭いだ。それもおびただしい量の火薬臭。次の瞬間、虎は立ち上がり、見るものをすくみ上がらせる大迫力で咆哮した。すると一瞬、虎が電撃を受けたようにのけぞり、もんどり打って倒れた・・・・。 




















 ベンガルタイガーはもの珍らしそうに密林を眺めた。
ベンガルタイガーはもの珍らしそうに密林を眺めた。
虎のいるそこは、波打つような凹凸を繰り返す密林の頂上部分に位置し、木立の切れた辺りから鬱蒼たる原生林が続いている。
ベンガルタイガーは「ふう」と息をつき、「やっと出られた・・・・」と感慨深げにつぶやいた。










 そのとき彼は知るすべもなく、まさか数十頭にもおよぶ虎たちが自分を捜していようとは・・・・。それらは湿原を彷徨っていたり、草原あるいは岩場を徘徊していたりと、様々な場所から、彼ベンガルタイガーを追っていた。
そのとき彼は知るすべもなく、まさか数十頭にもおよぶ虎たちが自分を捜していようとは・・・・。それらは湿原を彷徨っていたり、草原あるいは岩場を徘徊していたりと、様々な場所から、彼ベンガルタイガーを追っていた。










 マンシュタインは男を追っていた。
マンシュタインは男を追っていた。
“ここにいるはずだ……”“やつはここにいる!!”
マントイフェルは主を探していた。
“どこにいるのだ!!”
“この森のどこかに…………かならずいる……”
カンネルは王を探していた。
“王よ、今どこにいらっしゃいますか??”
“あなたがいなければ、私はありません。あなたが往くところ、私はどこまでもついていきます。なぜならば、そこが私の戦場なのですから……”
そこから何千キロも離れたアフリカ南部、サバンナのマライア保護区。まだ生まれて数ヶ月しかたってないライオンの双子がいた。とは言え野生動物の場合、多重出産がほとんどだから、双子というのもおかしい。彼らの場合も六つ子として生まれたが、ハイエナに襲われたり、コブラに咬まれたり、その他諸々で、とうとう二人っきりになってしまった。幼少期はさすが百獣の王といえども、ひ弱でただの獲物にすぎない。若きキングとプリンセスは特に仲がよく、食べるときも獲物を狩るときも、遊ぶときも寝るときも、いつもいっしょだった。
夕方になるといつものように、母親にくっついて狩りにでかける。メスばかりの群れで六頭、それにちっこいのが二匹くっついて走る。群れはインパラの匂いを嗅ぎつけて追い始めたようだ。インパラはライオンたちの好物であり、彼らのメインディッシュとしてあげられよう。
インパラはアフリカ南部に広く生息し、シカに見えるがじつはそうではないらしく、ウシ目、ウシ科に属するりっぱなウシ?だ。じつはシカ自体もウシ目に属し、ウシの仲間であるらしい。生物学的に見れば太古に牛と馬に別れ、シカは牛のほうに分類されるということだ。
インパラ――土地の言葉で「黒い足」と呼ばれるこのシカ(シカといったほうがわかりやすいだろう。日本人にはどう見ても牛には見えない)は、ジャンプ力、脚力は最強であろう。七、八メートルの川はゆうに飛び越えてしまう。
雄ライオンは現在縄張りのパトロール中で、狩りには参加していない。雌たちば何のパトロールやら?どうせ発情のフェロモンをプンプン匂わせた若い雌ライオンのお尻でも追っているのではないかしら?!"と、お互いに目配せし、鼻をフフンとならせ、また行進を再開した。
今日のばあい規模こそちいさいが、まさしくプロのハンターたちの行軍である。実はあと二つ雌の群があり、それぞれ七、八頭で活動している。やはりそれぞれが二、三頭の子供を養っている。養っているのは子供だけではないのだが・・・・。
これらの雌たちはすべて一頭の雄ライオンに直結している。彼に従う他のたくましいオスや、まだ経験未熟な若いオスたちは、キングのおこぼれにあずかるか、フリーのはぐれメスライオンを狙うのだ。
そのときプリンスは、初めて草原にはそぐわない異質な臭いをかぎつけた。母親たちは落ち着いていて、いつもと変わらずといったふうに歩みを続けている。するとにわかにメスたちの動きが慌ただしくなった。
かなり離れているが、インパラの群が大慌てで草木の間を走り去るのが見えた。
メスたちはさらに速度を速め、インパラの群の方向に走り出していった。
ところがプリンスは持ち前の好奇心から、先ほどの臭いの正体を確かめるべく、親たちとは回れ右してあらぬ方向へと走り出した。
プリンセスも兄の気配を感じないのが気になり、ふりかえると、兄が別方向へ走り去っていくのが見えた。妹はなんのためらいもなく、兄に置いていかれまいと必死に走りだしていた。
若獅子がみたものは、あとでわかったことだが、人間という生き物と、車という半分生き物のようなものだった。
プリンスはまたあるものに興味を示した。その人間にくっついている赤いヒラヒラしたものがどうしても気になり、ついに我慢しきれずにブッシュのかげから飛び出していった。
アリスは草原のそよ風に吹かれながら、パパたちの戻ってくるのを待っていた。とその時、何かが足にぶつかってきた。フワリと軽く、しかも動いているから生き物かもしれない。まだアフリカについて間もないアリスは怖いもの知らずで、興味津々に下をのぞき込んだ。
するとまだ小型犬ほどの子ライオンが、子猫のようにじゃれついているではないか。
「アハハハ」アリスは思わず笑った。これが将来、サバンナの帝王とも呼ばれる、すこし大きめの猫であるとも露知らず…………?!
アリスが時たまぶつかる子ライオンの柔らかみを味わっていると、さらにもうひとつの塊がぶつかってきて、目をでっかく広げて驚いた。
プリンセスはアリスのお尻のあたりにぶつかった。そこはグニャリと柔らかく、まだライオンの筋肉質な感触しか知らない子ライオンにとっては、はじめての経験だった。
だが、まだ遊びざかりの彼女にとっても、お目当てはやはりスカートのヒラヒラだった。
アリスは二頭ものライオンにもてあそばれ、最初は閉口していたが、すぐになれ、わざとスカートをひるがえし、右へ左へと回転しながら戯(たわむ)れて遊んだ。少女の着けている赤いスカートは、母ジェニファーが草原で見失ってもすぐにわかるように、本国イギリスで選んだものだった。アルプスの少女ハイジをイメージして、「サバンナの少女アリス」を演出させようとのジェニファーのもくろみだった。
草原に赤いドレスを翻(ひるがえ)し、それにたわむれて遊ぶ二頭のライオンと少女。まさに一幅の絵であった。
ベンガルタイガーは自分が何者であるかわかっていた。
それもそのはず、おれは今まで地獄にいたのだ。死んでからいったいどれだけたっているのかまったくわからない。地獄には時間の観念がまったくないのだ(ふつう人間でも真っ暗い部屋の中にずーっと閉じ込められていたら、時間、月日、年月などもまったくわからなくなるだろう)。
そんななか、ようやく動物にならば生まれ変わることが出来るのを突き止めた。
ベンガルタイガーはそろそろ腹が減ってきた。
ベンガルタイガーは丘を下り再び森へと入っていった。
自分が虎であることはわかっていたが、
とにかく仲間のところにいかなければ。
雌の臭いを嗅ぎつけた。子供が二頭はいるようだ。他にいく充てもないので、何気なく追いかける。二日追いかけて、ようやく追いついた。
親子は水場で一息いれている。
ベンガルタイガーは、迂闊(うかつ)に近づいてメスを驚かしてもいけないと思い、様子を見ていると、メスの回りで違和感のある動きのあるのが見えた。。
密猟者だ。
あれから五、六十年はたっているとはいえ、人間のやることはだいたいわかる。
虎の皮は高く売れる。生活のために、あるいは単に金をもうけるために、人間たちは平気で動物を殺す。これも弱肉強食の一端であろうか。
本能的にトラは攻撃態勢にはいった。今は彼も狩られる側なのだ。
マイリーは金髪の時のほうがすきだな。マイリーサイラスでなく、ハンナモンタナのほう。
「シークレットアイドル」では、主人公の名前がマイリーだから、本名を使っていて、ややこしいけど、金髪のかつらをつけて、ハンナモンタナに変身する。あああ!!! ややこしいけど、だから、けっきょく、普段のことをそのまま番組にしたんだよね。
あああ!!!ややこしいけど、まさかマイリーが本名だっとはた。たしかにマイリーサイラスよりも、ハンナモンタナのほうがインパクトが強いんですよ。おじさん、何度だまされているのか、まじでハンナモンタナっていう歌手がいるんだなと思ってた。それだけならまだいいけど、番組のなかのパパが本物のお父さんだったなんて。
<おじさんがトラックのなかで足を二本とも乗っけて、携帯を両手でかかえ、何を熱心にメールしているのか? 見てみたらハンナモンタナ、>


 恐えー!!
恐えー!!





第一章 異次元世界との接触
ことの起こり
私は二つの顔を持つ。昼間は人間と交際い、夜は霊たちと交際う。外見上はふつうの人間と変わらないが、裏では霊とのさまざまな駆け引き、交信を行っている。異次元世界との接触……。いったい、いつ頃からこうなってしまったのだろう 。
二十年前
ここは木曾の山中である。
高校に入ったばかりの私は、科学的にいう四次元の世界、異次元空間などに興味を抱いていた。退屈な毎日とおさらばしたかった。いっそ四次元の世界にでも翔んでいってしまおうとさえ思った。現実からの逃避である。その時、現実生活の中で、たった一つだけ四次元世界への入り口を思わせるような出来事があった。それは“金縛り”現象であった。
この〈金縛り現象〉が、私を異次元世界へと引きずり込んでしまった。あとで後悔してももうおそかった。悪魔に魅入られたというのだろうか? だが、相手が霊界だったから、まだましなほうである。こうなるのは定めだったのか ?いや、数奇な運命をたどるべく、最初から仕組まれていたのだ。
私は小さなころから何度となく金縛りにあっている。その度に夢中で体を動かしてその呪縛から逃れていたのだが、ならばいっそ、逃げないでいればどうなるだろうか? そこに異次元世界の謎が隠されているような気がした。
私は異次元世界を覗こうと決心した。逃げないでいる 。実行するにはいささか勇気がいった。死ぬかも知れない。戻れないかも知れない。最悪の状態を想定するなら、自分がその異次元世界から帰ってこれなくなり 実際、そういった事例もある 肉体は仮死状態になるかも知れなかった。
金縛りになるのは夜ふかしをして、かなり頭がボウッとしてきた深夜、ウトウトッとしたころになりやすい。だからその日も明けがたまで起きていて床に入り、金縛りになるのを待った。
何にも考えないでいれば、スーッと寝てしまうのだが、これが妄想をいだくようになってくるとかなり危ない。妄想というか夢見心地というのか、ウツラウツラしていて夢と現実のはざまを行ったり来たりしていると、突如として金縛りに襲われるのだ。ふつう考えておかしくなるようなことが 睡眠不足が度を超すと幻影を見るようになるという 頭の中で映像化されていった。脳みそがかなりくたばってきたのか、おかしなことばかり考えていた。
すると、いきなり“バシッ”という衝撃を受けて、金縛りになったのだ。
もうすでにまったく異なった世界に入っていた
しばらくして体が「ギューン」という音とともに、かなり速いスピードで回りはじめ、ななめ下方へと降下していった。
ようやく回転がおさまったので、ゆっくり目を開けてみると、何と真夜中のはずなのに、真昼の“和室”が目の前にあるではないか。江戸時代の武家屋敷や茶室などにあった「書院造り」。いま目前にある部屋はまさしくそれだった。けっして虚像でもない、幻でもない、恐ろしいほどのリアルな空間がそこにあった。 ちょうど“違い棚”のある床の間のわきから、眩いばかりの朝日が射し込んでいた。
「エッ!そんな馬鹿な?」今はまだ真夜中ではないか。
「ひょっとしたら時間を超越して、もう朝になってしまったのだろうか?」
部屋の造りは新築同然で、木の香りや畳の匂いがただよってきそうだ。歩くというより前にスーッとすべるような感じで、つづきの間へと入っていった。途中、部屋の仕切りの“らん間” 天井と襖のあいだにある、透かし彫りなどの板をはった部分 が見えた。これもなかなかこった彫刻をほどこしてある。
しかし残念なことに、それから次第に目が閉じられていって現実にもどったのだが、何ということか現実の世界ではまだ夜のままだった。時計を見るとさほど時間はたっていなかった。何とも狐につままれたような心境であった。
だいたい、このころの高校生活の思い出を再生してみても、スモークのかかったあまりハッキリしない映像しか映し出されないが、この異次元世界での出来事は、ハイビジョン映像のように鮮やかに記憶に残っている。そして驚くことにこの二〇年間を振り返ってみても、現実の記憶よりも異次元世界の記憶のほうがより鮮烈に残っているのは、不思議というよりほかない。
またこの時もつぎの時も、やや離れた後方に誰かいて、じっと私を見守っている気配を感じた。その者がこの世界に誘導しているのかという気もしたが、ただ目の前の美しい世界に見入っているだけで、とても振り返ってみるような余裕はなかった。またその者たちも私に気づかれないよう、けっして接触してこようとはしなかった。
だが異次元世界の住人たちは 哀れな子羊を虜にすべく 着実にそして計画的にジワリジワリと迫っていたのだ。そして……。
安心しきっていたある日、世にも恐ろしいことが起こったのだ。
幽霊出現
その日、居間でテレビを見ていて眠くなり、寝転がって微睡んでいた。
“いい気持ちだ……。電気もつけっぱなしだけど、まあいいか……”
すでに頭のなかでは理由のわからないことを考えている。夢か現か……。と、その時 。
バシッ
“金縛りだ!!” 全身を打たれるような衝撃でわれに返った。さきほどまでの妄想は跡かたもない。が、こんどは体が動かない。強烈な呪縛で身動きできないのだ。それに世界がおかしい。それまでの暖かかったコタツの温もり、テレビの雑音、居心地の良い居間の雰囲気などすべてが吹っ飛び、一種異様な世界が荒涼と広がっている。気が変になりそうなおかしな音まで聞こえて来る。ここにはいったい現実の世界を指し示すようなものが存在するのだろうか?
真っ暗やみだ
何も見えない。しばらくすると、周囲に無数の霊が集まってくるのを感じた。
幽霊に限らず、霊はみな、身の毛のよだつというか、心底から“ゾオーッ”とするような〈霊気〉ともいうべき気を発する
“ワッ!幽霊だ!!” 一人?だけで十分なのに、いったい何人いるのだろう。ホラー映画としか言い様のない世界だった。
男の声……女
訪問者1255人目





















 ベンガルタイガーはもの珍らしそうに密林を眺めた。
ベンガルタイガーはもの珍らしそうに密林を眺めた。









 そのとき彼は知るすべもなく、まさか数十頭にもおよぶ虎たちが自分を捜していようとは・・・・。それらは湿原を彷徨っていたり、草原あるいは岩場を徘徊していたりと、様々な場所から、彼ベンガルタイガーを追っていた。
そのとき彼は知るすべもなく、まさか数十頭にもおよぶ虎たちが自分を捜していようとは・・・・。それらは湿原を彷徨っていたり、草原あるいは岩場を徘徊していたりと、様々な場所から、彼ベンガルタイガーを追っていた。










 マンシュタインは男を追っていた。
マンシュタインは男を追っていた。

 恐えー!!
恐えー!!




